米原市 青岸寺のスギゴケとイワヒバ
2018年07月27日

青岸寺の庭のすばらしさは石組にある。大小無数の石が庭を埋めている。さまざまな表情をもつ石が、自然がつくり出した姿のままに座っているように見える。
不動の存在感をもつ石に対し、水は自在に流れている。背後にせまる山から水がなめ滝となって石のあいだを流れ落ち、幾筋かの流れを経て、澄んだ水を湛えている。
水は、すべて苔で表現されている。青岸寺の庭は、水を青いスギゴケで表した枯山水庭園である。
寺は、室町時代に近江の守護職であった佐々木京極導誉が開いたという。16世紀のはじめに兵火で焼失し、江戸時代に入って彦根大雲寺の和尚によって再興された。
庭もそのとき造られたが、彦根の楽々園が築庭される際に、青岸寺の庭から石が持ち出された。現在の庭園は、後にときの青岸寺和尚が楽々園の作者に築いてもらったものだという。
庭には、変化する自然を象徴するものがもう一つある。イワヒバである。岩檜葉と書き、別名を岩松ともいう。葉がヒノキに似ており、姿はハイマツのようだ。
深山で風雨や寒さに耐えて岩場を這う低木の針葉樹のようだが、イワヒバはシダ植物である。日照りの時期には枝と葉が丸く縮んでいるが、雨を受けて水を含むと鱗状の葉が青く色づく。だから復活草ともいわれる。
水に見立てたスギゴケも、雨のない日は枯れ草の色合いをしているが、水を得ると青々とよみがえる。動かない石に対して、千変万化の苔とシダが配されている。


Posted by 風まかせ at 19:30│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|


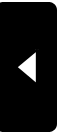
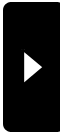
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。