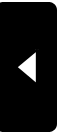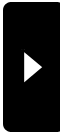井伊神社のシダレザクラ
2018年03月31日

佐和山の西麓にある井伊神社の境内に、シダレザクラの巨木がある。しなやかに流れる枝に薄紅色の花が咲き乱れる。
シダレザクラは、自生する桜の種エドヒガンをもとに作られた園芸品種だといわれる。平安時代から庭木として植えられていたともいう。同じ園芸品種のソメイヨシノとは違って長寿の樹が多く、名木が多い。
井伊神社は、彦根藩12代藩主井伊直亮が先祖の地である遠江国の井伊谷から八幡宮を分霊して、創建した宮が始まりである。もとは隣の龍潭寺の境内にあったが、明治の神仏分離令により現在の地に移された。
天保13年(1842)の創建というから、170年あまりを経過しているが、社殿は朱塗りの柱や極彩色に塗られた彫刻などに創建当時の華やかさを感じさせる。現在は老朽化のために屋根の覆いがされており、内部を覗うことはできないが、天井にも色とりどりの草花が描かれているという。
井伊直亮は、直弼の21歳年上の兄で、直弼の一代前の彦根藩主である。洋書の購入や蘭学者の登用を推奨し、西洋式軍隊の練成に努めたという。
シダレザクラは、一説では直弼のお手植えだと言われる。見るからに老木だが、神社が龍潭寺から移転する前からあったのだろうか。樹齢は170年を超えているように思う。
龍潭寺にもシダレヤナギがある。八重のベニシダレである。山門を抜けた先に、やや濃い紅色の花を枝いっぱいに付けたサクラの樹が現れる。
こちらの樹は、井伊神社の樹ほどの齢を経ていないが壮観である。散り際もいい。苔むした参道に、ひらひらと紅の花弁が落ちてゆく。
Posted by 風まかせ at 18:53│Comments(0)