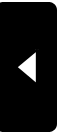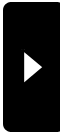伊香具神社の八重桜
2018年04月13日

サクラの種類はかぎりなく多い。日本に自生する種類は10種ほどだが、古今それらをもとに作られた園芸品種が800を数えるという。
野生のサクラは山桜、園芸品種は里桜と呼ばれるが、里桜は、いまに残る品種が200を下らないというから、素人には里に咲くサクラの名を当てることがむつかしい。
花見は、江戸時代につくられたソメイヨシノに席巻された感がある。華やかさはすばらしいが、画一化されていく時代の象徴のようでもある。
国文学者であり民俗学者でもある折口信夫によれば、花見は豊作の予祝から来ているというから、あの喧騒はお祝いの行事だと割りきればよいのかもしれない。
だが、神に祈るという意味からいえば、サクラは八重咲きの方がふさわしい。歴史が古いし、古代は八重咲きのサクラが多かったようだ。
万葉集にも「奈良の都の八重桜」という歌があるというから、1200年も前に八重咲き品種が庭に植えられていたことがわかる。
八重咲きのサクラといえば、賤ヶ岳の南麓にある伊香具神社のサクラがある。ソメイヨシノの花が終わって、ようやく花を開きはじめる。
伊香郡には『延喜式』の神名帳に載る、いわゆる式内社が46もあり、近江にある式内社の3分の1を占める。なかでも伊香具神社は、古代から社格の高い大社に列せられ、伊香郡の総鎮守の地位にあった。
賤ヶ岳は万葉の時代には伊香胡山と呼ばれた。山の南麓にある大音の集落の入口に、「伊香具神社」と刻まれた石柱と鳥居が立っている。神社に続く参道は長番場と呼ばれる。200メートルあまりある参道が、新緑の季節にヤエザクラの薄紅の花で彩られる。
Posted by 風まかせ at 13:29│Comments(0)